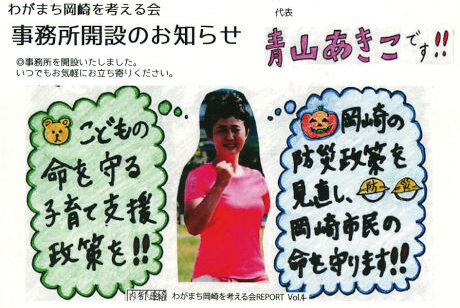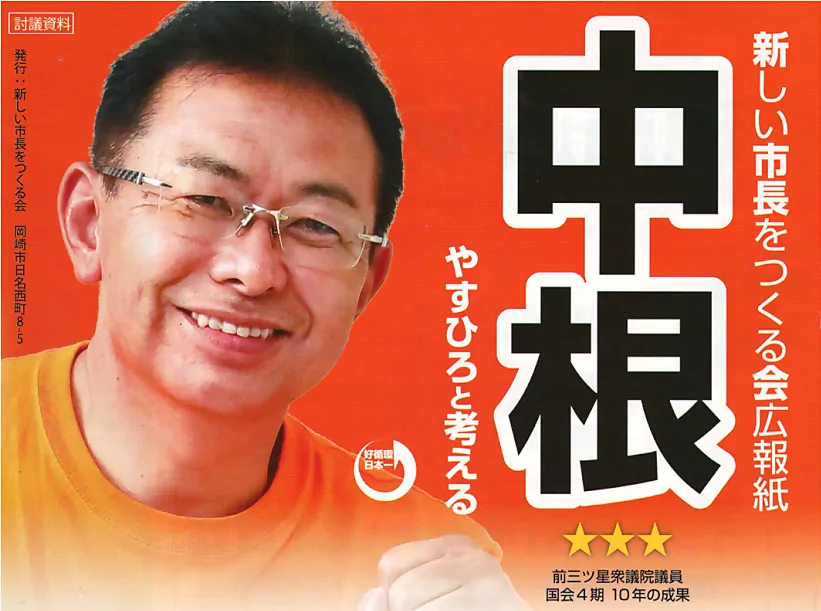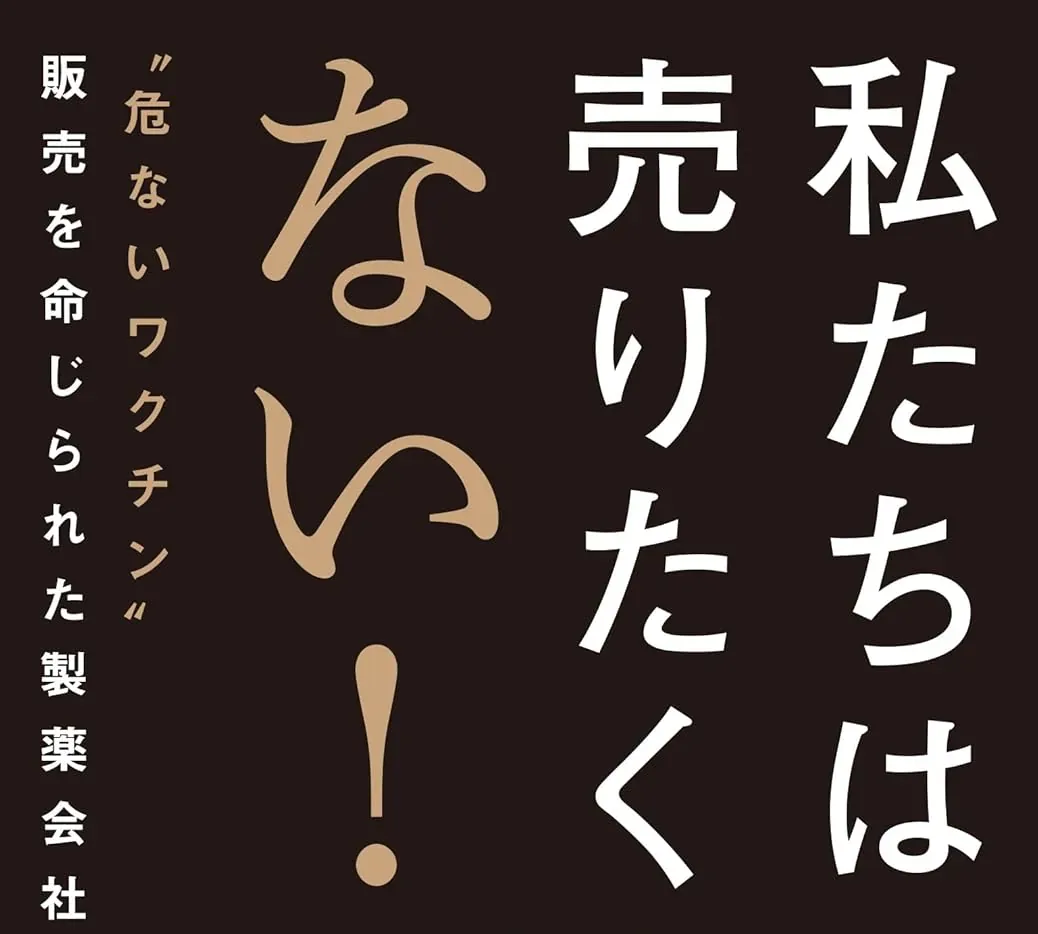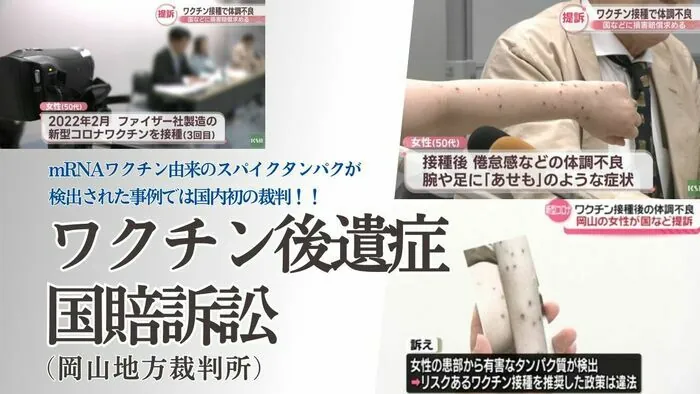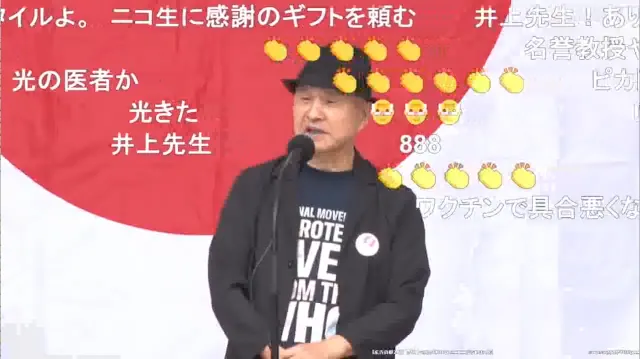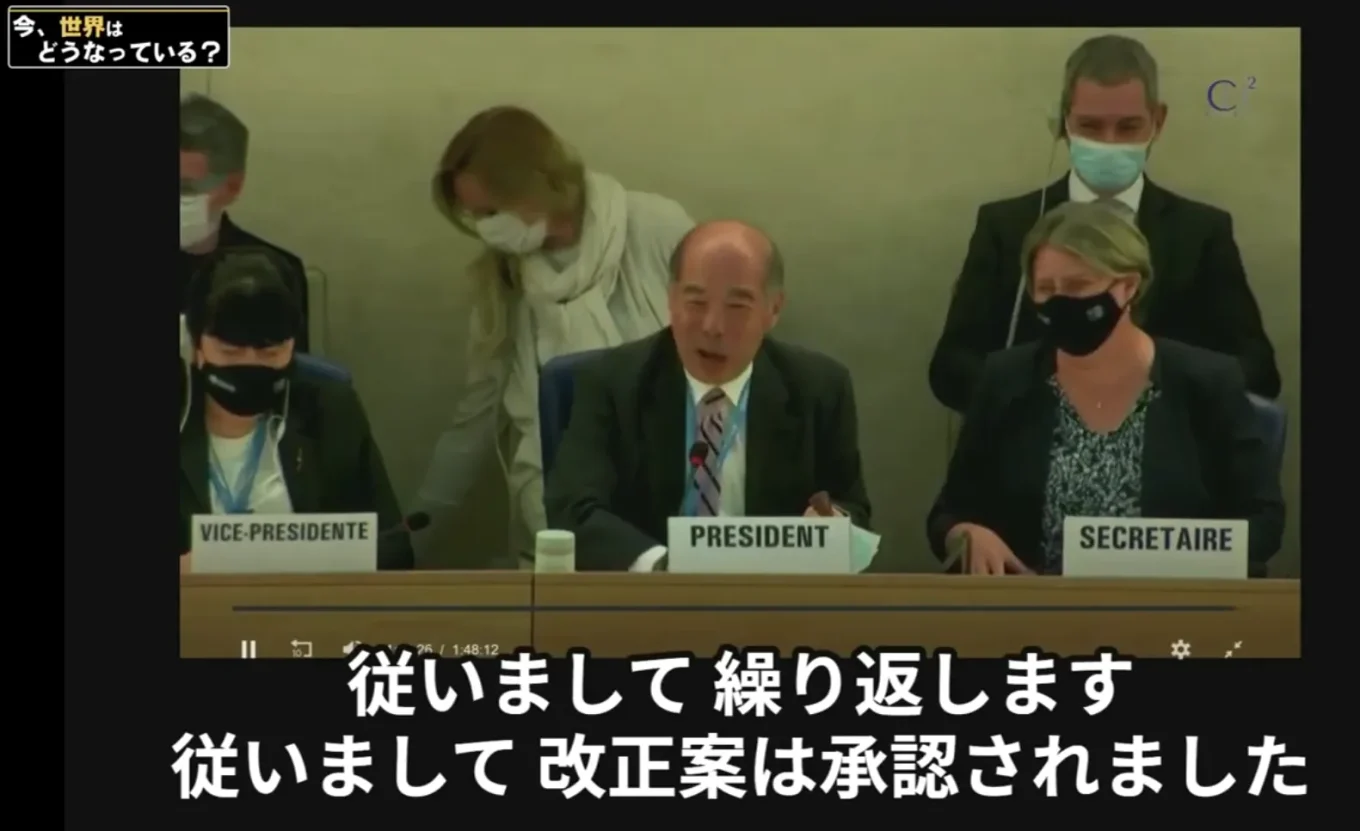昨夜、ネットニュースの中でふと目に留まった記事が有った。
三浦瑠麗氏インタビュー「日本学術会議はちぐはぐな組織。それでも、パンはパン屋の言うとおりに作らせておくのが『保守の知恵』です」
参照:https://bunshun.jp/articles/amp/40790?page=1

週刊文春といえば「文春砲」とか言って、色々なスキャンダルな事件を暴く、下世話な週刊誌!というイメージだったので、これまで読んだことが無かったのだが、このタイトルに何故か気がひかれた。
三浦瑠麗という名前は、どこかで聞いたことがあるような気がするが、正確には何者か分からないという状態でした。
パンはパン屋の言うとおりに作らせておくの『保守の知恵』という部分にたぶん反応したのだろう。
少し難解だけど、記事全文を引用します。そうでないと伝わらないものが大きくなりすぎると思いますので。
三浦瑠麗氏インタビュー「日本学術会議はちぐはぐな組織。それでも、パンはパン屋の言うとおりに作らせておくのが『保守の知恵』です」
菅義偉首相が、日本学術会議が推薦した新会員候補105名のうち6名の任命を拒否した問題が波紋を広げている。
三浦瑠麗氏インタビュー「日本学術会議はちぐはぐな組織。それでも、パンはパン屋の言うとおりに作らせておくのが『保守の知恵』です」
菅義偉首相が、日本学術会議が推薦した新会員候補105名のうち6名の任命を拒否した問題が波紋を広げている。
1949年に設立された日本学術会議は「学者の国会」とも呼ばれ、政府から独立した専門家の立場で、社会のさまざまな課題について提言を行う機関だ。現在の会員は210名。任期は6年で、3年ごとに半数が交代する。
日本学術会議法では、同会議を「独立」した存在と規定し、会員は「内閣総理大臣が任命する」としているが、政府は1983年に当時の中曽根総理大臣が国会で、「政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っている」と答弁。
あくまでも形式的な任命制であって総理に任命の拒否権はないという解釈を維持してきた。
しかし、今回の問題が起きる前の2018年に、その解釈を変更し、拒否権があるという新解釈に改めたというのだ。そして、その解釈に基づき今回、宇野重規東京大教授、加藤陽子東京大教授ら6名の任命を拒否した。
日本学術会議はあくまで政府に「助言」をする機関
任命拒否の理由は未だに明らかにされていないが、6名はいずれも安倍政権で特定秘密保護法や平和安全法制に反対した研究者でもある。
菅政権のこうしたやり方に対して、「学問の自由への露骨な侵害だ」「菅首相は説明責任を果たすべきだ」などと各学会や各研究団体が抗議声明を発表。野党も国会でこの問題を徹底追及する構えだが、果たして今後どう展開していくのか。国際政治学者の三浦瑠麗氏に、今回の問題の「核心」を聞いた。
菅首相はテレビ番組で、官僚に対して「政策に反対する者は異動」と言いました。政府の指揮命令系統に入っている一般の国家公務員に対しては、これは当たり前の話です。違法性も何もない、通常の指揮命令に対して、ただ単に自分が好まないからと、正当な理由もなしに命令を拒否すれば、これは明らかな服従義務違反。ですから、配置換えされてもおかしくない。
しかし、日本学術会議に関して言えば、政府の中の統治機構の中にあるのではなく、その横にいて、あくまでアドバイスをする存在ですから、むしろ彼らは独立性を保って、独自の意見を持って提言を行うことがもとめられる。政府がやりたいことをやるための機関ではなくて、その人たちが独自に生み出す考えを述べてもらった方が、日本の政治のためになるし、日本国民のためになるという発想が基になって作られている組織です。
ですから、確かに菅首相には「任命権」がありますが、特定の学者の業績や政治的意見に基づいて任命を拒否する能力は政治家にも官僚にもありませんし、またそうすべきでもありません。日本学術会議は、存在すること自体が対外的にも意味を持っているわけだから、政府が正しいと考える主義主張を共有する必要はない。逆にあくまで「助言」をするだけですから、彼らが言ったことを政府が聞く“必要”も必ずしもないわけです。
パンを作るのはパン屋に任せる
しかし、菅政権はそこにあえて手を突っ込み、6人の任命を拒否しました。人事に手を付けた背景には、日本学術会議を改革したいという気持ちがあるのでしょうが、それは6人をいきなり任命から除外する理由にはならない。この6人を除外した理由は明らかにされていませんが、今のところは彼らが特定秘密保護法や平和安全法制に反対した研究者であったことが関係したようにしか見えない。そうでないのならば、個々人の資質ではなく行政機構改革的な観点からの理由(男女比、学術分野構成比など)に基づく人事であることを説明する必要があります。
なぜ個々人の資質で任命するかしないかの判断をしてはいけないのかというと、政府が学者がなんらかの政治的意見を表明したことを問題視し、そのことによって彼らに制限を加えることは、「理念としての学問の自由」を侵害する可能性が生じるからです。
「理念としての学問の自由」とは何か。これは簡単にいえば、どんな学問をするかは学者に任せるということです。つまり、パンを作るのはパン屋に任せるということですね。
そうすれば、ある程度自由にパンを作れる環境があり、また若い職人の指導や発掘をプロのパン職人がすることになります。中には政府や国民にとって「美味しいパン」を作る職人も出てくれば、逆に「まずいパン」をつくる職人もいる。しかし、仮にまずいパンであっても、美味しいパンも含めてプロの世界に任せて保全しておくのが学問の自由を羽ばたかせることにつながるのです。例えば今は「まずいパン」に見えても20年後に花開くことがあるかもしれないし、本当にまずいパンを作る人がいても、その無駄があってこそ学問全体の豊かさが保たれる。
パンを作ったこともない人が、自分の感覚としてのパンの「うまい」「まずい」を押し付けるとどうなるか。「俺にとってうまいパンだけ作れ」と言い、「学問の自由」を守っている保護膜を破ってしまったら、世の中にはその時みんなが考える「うまいパン」しか残らず、学問の多様性はたやすく崩壊してしまうでしょう。それは、進歩もなければ深みもない社会で、後には何も残りません。市場原理は必要ですが、市場原理に基づかない専門家による判断が幅を利かせる領域を残しておくべきだというのはそういうことです。だから、多少傷んでいたりまずかったりしても、おおらかな心で、10億円ぐらい与えて、自由にさせるのがよいと考えます。
こうした考えは、これまでの自民党の政治家が持っていた「保守の知恵」だったとも思っています。「保守の知恵」が失われつつあるのは、小選挙区制度が導入され、政権交代を経験して以降、自民党も官僚機構も変質したから。しかし、そもそも政権がこんなちっぽけな人事にまで手を突っ込むようになったのは、学術の豊かさが社会に与えるものに対してあまり希望や期待を持っていないからでしょう。スペースシャトルや自動運転技術のように時代を大きく変える技術でなくても、人間にとっては学びそのものが喜びであり、人生に豊かさを与えてくれる一般書の背後にはたくさんの研究があります。それを伝えきれていないとすれば、政治や官僚の問題を指摘するだけでなく、学術の側ももっと頑張らなくてはいけない。
日本学術会議が全く問題がない組織であるとはいえません。正直にいって自己改革をしないといけないちぐはぐな組織であることは間違いありません。例えば、2000年ごろの日本学術会議の会員の女性比率はわずか1%でした。当時の社会標準に照らしても著しく遅れていたと言わざるを得ない。今はだいぶ改善していますが、自己改革しなければならないことはたくさんある。無駄に権威主義的であり、アカデミア一般の弊害と同様、人脈が重要視されすぎるなど、様々な問題を抱えています。
政府や日本学術会議、国民にとって一番いい解決策
政府は、学術会議が色んな点について問題があるという主張をここにきて盛んに出しています。もともとは「人事権」そのものに関心があったのは明らかですが、組織改革と絡める方向に行くことで、研究内容や政治的見解などのイデオロギー論争に流れるのを避けたのでしょう。学術会議の在り方の問題は、それはそれで改めて考える必要がある問題です。政府は6人の任命を拒否してしまった以上、もはやその人事を完全に撤回することはできないでしょう。しかし、批判の声が大きくなれば、政権運営にも響いてくる。ダメージコントロールの観点からは、行政改革的な理由にひきつけてしっかりと説明するのが正しい選択です。
そうすると、今回の任命拒否に関してはこのまま押し切るしかないという結論になります。しかしそれでは不健全です。そこで菅政権は日本学術会議に対して、組織改革でやるべきことや人事の在り方についてこれから方針を示す必要があります。もし方針がでれば、それに対して日本学術会議から意見が出てくる。そうして新たな学術会議の在り方を検討していく中で、欠員が生じている6人について改めて埋めていく作業が必要になってくるでしょう。そこで時間をかけながら、今回承認しなかった6人を改めて任命していくというのが、政府にとっても学術会議にとっても、そしてひいては国民にとっても一番いい解決策になると私は思っています。
如何でしたか?
僕は正直い言って、しばらくは何を言いたかったのか判然としませんでした。
こんな論法があるのか!こんな考え方があるのか!そしてこれだけ理詰めの文を女性が書いたのか?!
すごく複雑な言葉が縦横に絡まっていて、それを頭の中でひとつひとつ分解していって、もう一度それを自分に分かり易い文法に構築しなおす。そんな作業を何回も行った感じだった。
ここで投げかけられていることは、これまでマスコミでもネットでも読んだことが無く、こんな方法・考え方もありうるのか!と瞠目せざるを得ませんでした。
週刊文春やるじゃん!
こんなすごいものを乗せる力があるんだね!
今までの潜入観念を捨て去り、真摯に向き合ってもよいと思わせるに十分だと思った。